中学受験、とりわけ公立中高一貫校の適性検査は、模試の結果と実際の合否が必ずしも一致しない。
これは私自身が娘の受検準備を見守る中で実感し、さらに身近な体験談から強く考えさせられたことです。
「模試の成績が下がり続けている。もう諦めるべきか?」
そう悩むご家庭もあるかもしれません。ですが、模試の判定がすべてではありません。
本記事では、
- 実際にわが家の娘が模試で大きく成績を落とした体験
- 成績優秀でも不合格となった知人のケース
- 公立中高一貫校の「合格の謎」
を体系的に整理し、模試の結果だけで諦める必要がない理由をまとめます。
わが家の娘の適性検査対策模試が合格圏外になった経緯
小学5年の春、娘は進学塾に入会しました。入塾時の偏差値は39.7と低めでしたが、その後努力を重ね、数か月で63まで上昇。一般的な学力テストでは順調に成果を出していました。
ところが、公立中高一貫校の受検に直結する「適性検査対策模試」では苦戦。
- 初回(6月):合格圏内
- 2回目以降:徐々に判定が下がる
- 11月:D判定(合格可能性ほぼゼロ)
つまり、模試を重ねるごとに合格判定から遠ざかるという現実に直面しました。
「努力しているのに成績が下がる」
これは本人にも親にも大きなストレスでした。
そんな中、知人から聞いた体験談が一つの救いとなりました。下記が対象の過去記事です。
今回の記事内容が、より分かりやすくなると思うので、貼り付けています。
過去記事:中学受験は5年生からでは遅いのか? 公立中高一貫校を目指す家庭のリアルと可能性
公立中高一貫校の合否に潜む「謎」
知人の娘さんは、現在高校受験を控える中学3年生。驚くべきは、彼女が中学受験時に経験したことです。
- 小6時点で偏差値70超
- 塾でも学校でも常に上位
- 発展クラスに所属
それでも、公立中高一貫校には「不合格」でした。
一方で、直近の高校受験では私立の難関校に特待合格。来月は県下トップのSランク公立高校を受験予定です。(※追記:その後、Sランク公立高校も無事合格したそうです)
成績優秀で努力家でも、公立中高一貫校に受からない。
この「謎」は、他の保護者にとっても衝撃だったそうです。
模試の判定と実際の合格者のずれ
さらに驚いたのは、知人の娘さんの年度での合否結果です。
- 模試判定:上位3名はいずれも「合格圏」 → 全員不合格
- 実際の合格者:模試で「合格は難しい」とされていた生徒が2名合格
模試は全国規模で適性検査に沿った問題が出されるため、精度は高いとされています。
それでも「A判定の子が落ちる」「D判定の子が受かる」という逆転現象が起こるのです。
この背景には、適性検査特有の「答えは一つでない」問題形式や、作文・思考力・個性といった評価軸があると考えられます。
つまり、偏差値や模試判定だけでは測れない要素が合否を左右しているのです。
諦める前に大切にしたい考え方
この体験から導かれる結論はシンプルです。
模試の結果だけで受検を諦める必要はない。
もちろん、基礎学力の定着は欠かせません。小学校で習う内容を穴なく身につけることが大前提です。
そのうえで、公立中高一貫校では以下のような力も問われます。
- 日常生活の中での体験や地域文化への理解
- 多角的に物事を考える姿勢
- 他者と異なる視点で表現できる柔軟性
これらは「模試の点数」には直接表れにくい力です。
さらに重要なのは、受検を続けるかどうかを決めるのは「模試の結果」ではなく「子どもの気持ち」であること。
親が先走って諦めるのではなく、子どもの意志を尊重する姿勢が大切だと感じました。

まとめ
未来を見据えて受検に向き合う
身近な実例を通して、公立中高一貫校の中学受検は「模試の結果=合格」ではないことがはっきりしました。
- A判定でも不合格はあり得る
- D判定でも合格は可能性がある
- 最後まで諦めない姿勢と日常での学びが重要
わが家も一時は模試の結果に一喜一憂し、視野が狭くなっていました。ですが、知人の体験談から「合格・不合格以上に、挑戦そのものが未来につながる」と気づかされました。
模試が思わしくなくても、それは単なる指標のひとつ。
子どもの努力や成長を信じ、最後まで伴走することこそ、親として最も大切なのだと思います。
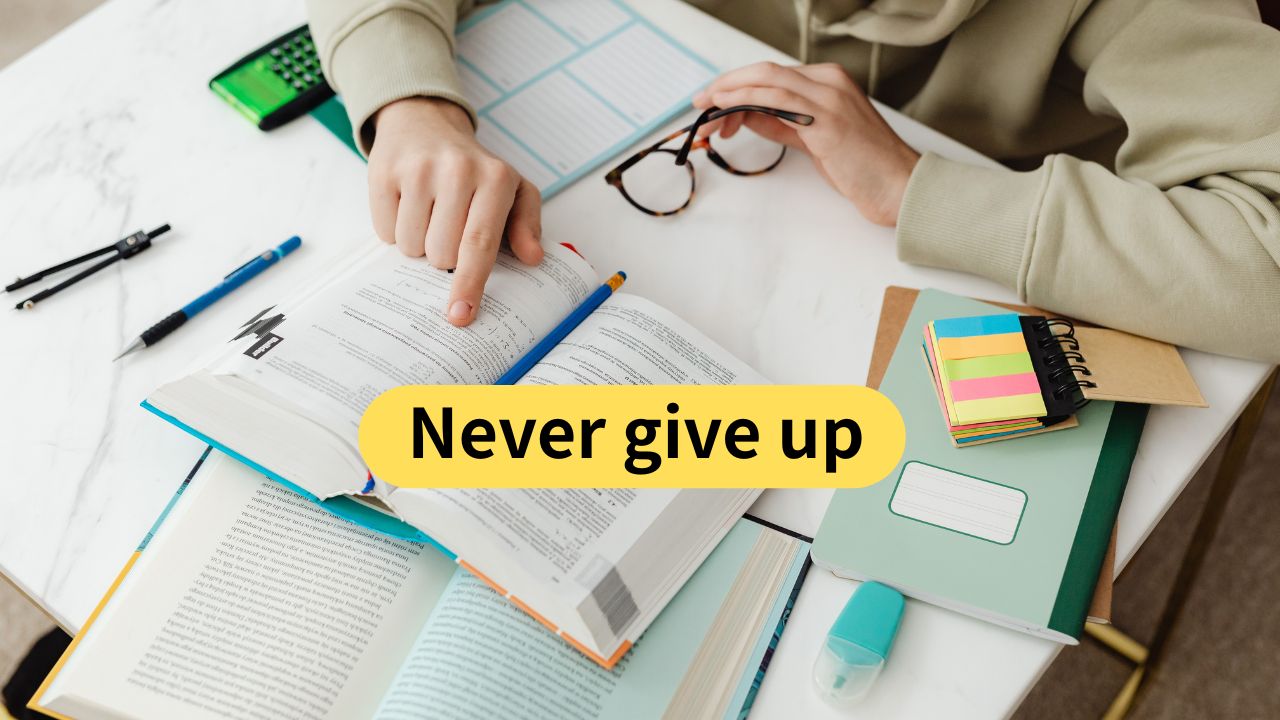


コメント