中学受験に挑戦する小学生にとって、「得意科目」と「苦手科目」の差は避けて通れないものです。
わが家の娘(小学5年生)も、塾での学力テストを通じて、自分の強みと弱点がはっきりしてきました。
この記事では、娘の学習を通じて見えてきた「苦手科目との付き合い方」と「得意科目を活かす戦略」について、体験談を交えながら整理しました。
同じように受験を控えるご家庭の参考になれば幸いです。
苦手科目の壁 ― 偏差値の伸び悩みと現実
娘は5年生の春に進学塾へ入塾しました。最初の偏差値は39.7。それを4か月で63まで伸ばすことができ、本人も自信をつけてきたように思います。
しかし、入塾から半年が経過した現在、成績は「横ばい」。高得点を取るためには、さらなる壁が待ち受けていると痛感しています。
実際、偏差値は上がれば上がるほど伸びにくくなります。70台を目指すのは簡単ではなく、基礎の反復に加えて「スピード」と「精度」が求められるからです。
算数対策の実例 ― ミスと時間配分との戦い
娘にとって一番の課題は算数です。
テストでは「全問解けるのに時間が足りない」と悔しそうに話すこともあります。
ケアレスミスの連鎖
計算問題そのものは日々の反復練習で安定しましたが、図形や文章題になると「途中式の書き方が雑で、違う数値を計算してしまう」というミスが頻発。(例:「3」が「2」に見えるなど)
特に算数は配点が大きいため、1問の失点が合否に直結します。
実際に娘の答案を見ていても、「解き方は正しいのに計算がずれる」ことが多く、まさにもったいない失点です。
時間配分の難しさ
もう一つの壁は時間配分です。
慎重になりすぎて前半に時間をかけすぎると、後半の大問で手が回らない。逆に焦って解くと、雑な計算でミスが出る。
娘が私に話すこと、

全問わかる問題なのに、時間が足りなくてゆっくりと解けないからミスをするんだよー。この大変な気持ち、ママにはわかる~?
結局のところ、「スピードと正確さの両立」が算数最大の課題だと痛感しています。
📌 親としての学び
- 問題用紙に途中式を丁寧に書かせる
- 「制限時間内で仕上げる練習」を家庭学習でも意識する
- テスト後は「どこで時間をかけすぎたか」を振り返る
こうした小さな習慣が、苦手科目克服の第一歩になると感じます。
得意科目を活かす戦略 ― バランスよりも「突出」も武器に
一方で、同じ塾の生徒さんの中には「算数は苦手だけれど国語と理科で偏差値を引き上げる」という戦略を取っている子もいます。
「得意科目を徹底的に伸ばして弱点をカバーする」
これも立派な受験戦略です。
公立中高一貫校の適性検査では、国語・算数・理科・社会の総合力が問われますが、必ずしも全科目が均等にできる必要はありません。
強みを武器にしつつ、苦手科目を「足を引っ張らない程度」に抑えることも合格への道です。
📌 ここでの親の役割は、
- 子どもの得意を正しく見極めること
- 苦手に過度に落ち込みすぎず、前向きに学べる雰囲気を作ること
だと思います。
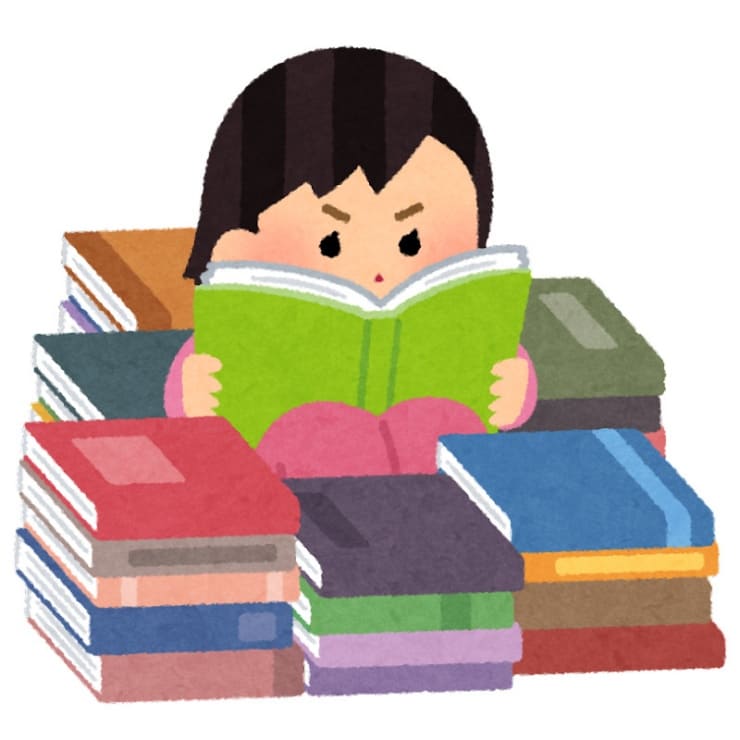
まとめ
苦手を放置せず、得意を最大限に活かす
中学受験は「苦手から逃げられない試験」です。特に算数はほぼすべての学校で必須科目。避けることはできません。
だからこそ、
- 苦手科目=ミスの原因を一つずつ潰す
- 得意科目=自信につなげて点数を稼ぐ
という両輪で対策していく必要があります。
娘もまだ計算のスピードや精度に課題を抱えていますが、「努力の積み重ねが必ず結果につながる」と信じて伴走しています。
同じように受験を目指すご家庭も、ぜひ「苦手をどうカバーするか」「得意をどう活かすか」を一度整理してみてください。
小さな工夫の積み重ねが、きっとお子さんの自信となり、合格につながるはずです。
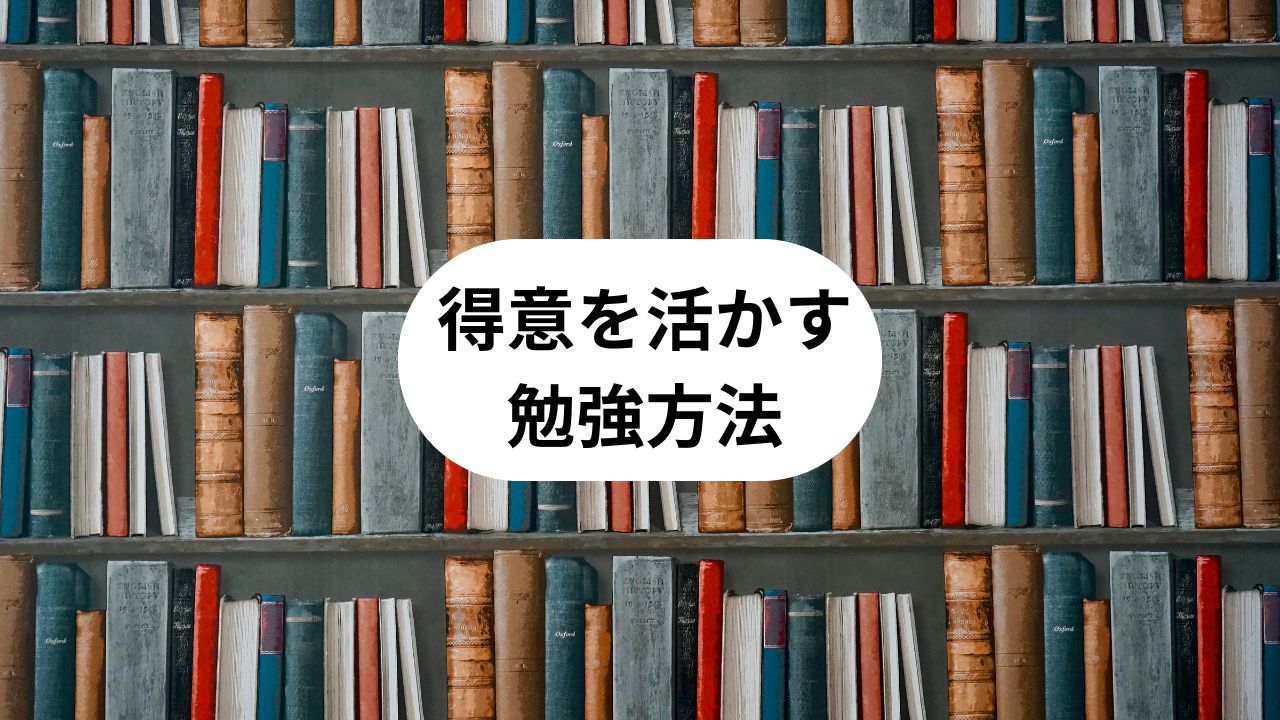


コメント