新年度になり、娘は6年生になりました。
志望校の一つである公立中高一貫校の公開授業に参加し、親子で授業を見学してきました。
率直に言うと、「中学生ってここまでできるのか」と驚かされるほどの授業内容で、特に社会性の高さとディスカッション力には圧倒されました。
この記事では、
- 公立中高一貫校の授業の様子
- 実際に見学して感じた「受検対策に役立つポイント」
- 将来の適性検査に直結する力
について体系的にまとめます。
公立中高一貫校の授業の特徴
見学した授業は、国語・数学・理科・社会・英語の5教科。
クロームブックを活用したICT授業が多く、スライドを使った発表形式が定着している印象でした。
同じ学年でもクラスごとに内容が異なり、学習の多様性と探究的な学びを重視していることが伝わります。
特に印象的だったのは、中学3年生の社会の授業。
単なる知識暗記型ではなく、複数の条件を比較しながら自分の意見を構築し、他者に伝える力を徹底的に鍛えている点でした。
【ケーススタディ】コンビニ出店シミュレーション授業
テーマ設定
授業テーマは「A市・B市・C市のどこにコンビニを出店すべきか」
人口動態・立地条件・補助金・競合環境などが提示され、各班がスライドを用いて分析・発表しました。
各市の条件(抜粋)
- A市:病院との複合、人口減少、補助金300万円
- B市:工場や住宅開発あり、競合多数、24時間営業
- C市:大学との複合、人口増加、出店費用高め
発表形式
- 前半:各班が5分間で見学者へ個別プレゼン
- 後半:クラス全体で発表&ディスカッション
生徒たちは「メリットとデメリットを比較し、数値データやグラフを根拠に論理的に説明」しており、大人顔負けの内容でした。

ディスカッション力の高さに驚いた場面
特に印象的だったのは、多数派(C市支持)と少数派(A市支持)の議論。
- C市派 → 「立地・人口増加・大学複合で安定した集客が見込める」
- A市派 → 「病院との複合・営業時間設定・人口増加につながる可能性」
少数派は不利かと思いきや、Googleマップを用いた立地説明や「住民の心理」に基づいた人口増加の論理展開など、非常に説得力のある主張を展開していました。
ここで重要なのは「正解のない問いに対して、多角的に考え、自分の意見を相手に伝える力」が鍛えられている点です。
これはまさに、公立中高一貫校の適性検査の本質に直結しています。
公立中高一貫校が育てる「3つの力」
公開授業を通じて見えた、受検に直結する力は以下の3つです。
- 柔軟な思考力
→ 単一の正解を求めるのではなく、多面的に考えを深める。 - 発信力(プレゼン能力)
→ データやグラフを根拠にしつつ、相手に届く言葉で説明する。 - 聞く力(傾聴力)
→ 他者の意見を尊重し、必要に応じて取り入れ、議論を発展させる。
これらは塾や家庭学習だけではなかなか養いにくい力であり、日常の授業や生活習慣の中で意識的に育むことが重要です。
我が子への示唆と受検対策への応用
公開授業を見学して強く感じたのは、「聞く力」が「話す力」を支えているということ。
- 授業中は私語がなく、他者の話を最後まで聞く姿勢が徹底されている
- 良い意見を吸収し、自分の発表に活かすサイクルが成立している
娘にとっても「相手の話をしっかり聞く姿勢」を普段の生活で意識することが、将来の適性検査の記述力や面接対策につながると感じました。
また、今回のような公開授業の見学は、受検勉強のモチベーションアップにも直結します。
「この学校で学びたい」と実感できることが、長い受験勉強を支える大きな力になるからです。
まとめ
公開授業は受検家庭に必見の機会
今回の公開授業で学んだことを整理すると
- 公立中高一貫校は、知識暗記型ではなく「考える力・伝える力・聞く力」を重視
- ディスカッションやプレゼンを通じて、適性検査に必要な能力を日常的に育成している
- 志望校見学は、受検生本人にとって強いモチベーションになる
受検を考えているご家庭は、文化祭や公開授業などにぜひ積極的に参加してみてください。
机上の学習だけでは分からない「学校の空気感」や「生徒の社会性の高さ」を、実際に体感できるはずです。
私自身、今回の見学で「日本の未来は明るい」と感じるほど、中学生の成長に驚かされました。
そして娘にも、普段の生活から「聞く力」を意識し、将来につながる力を伸ばしてほしいと思っています。
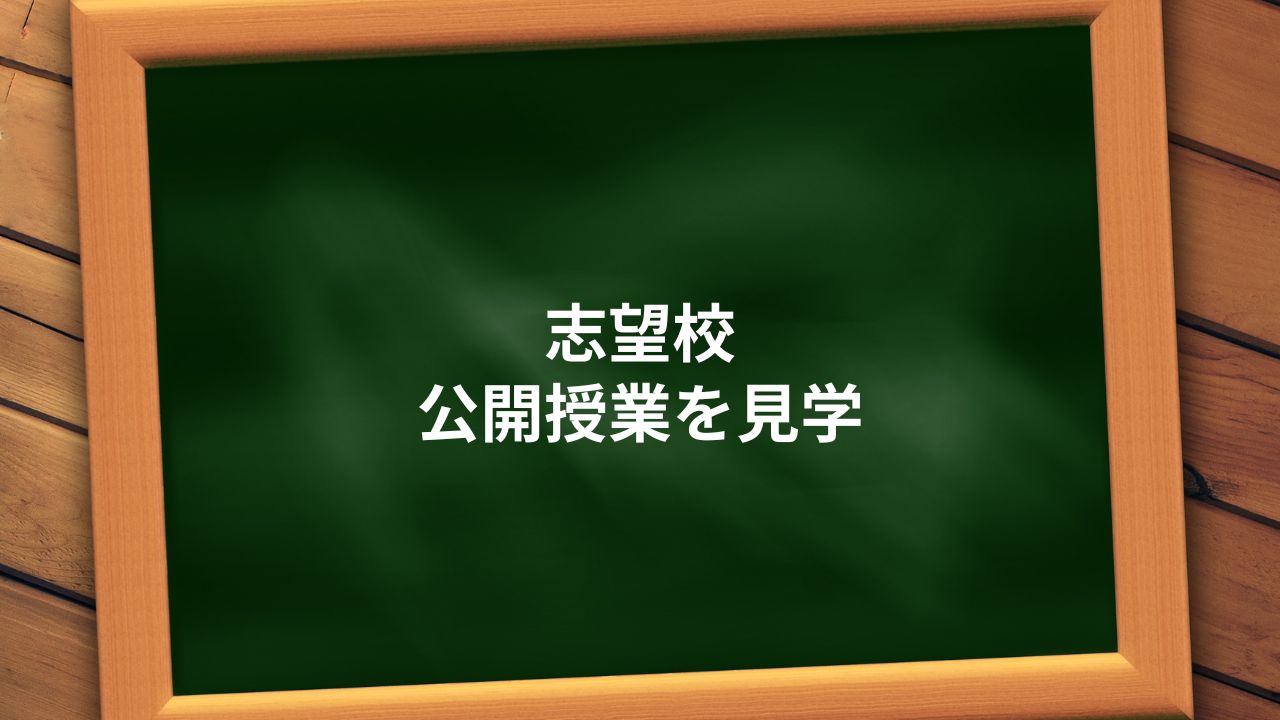

コメント