我が家の5年生の娘が、初めて適性検査対策模試を受けてきました。
まだ受験本番まで時間はありますが、今回の模試を通して「今から気をつけたいこと」や「日常の学習で意識すべき点」が見えてきました。
この記事では、体験談をもとに模試の内容や難易度、気をつけるべき勉強法を整理しました。これから模試を受けるご家庭や、公立中高一貫校受験を目指す方の参考になれば幸いです。
模試を受ける条件と概要
適性検査対策模試は、公立中高一貫校受験に欠かせない模試で、5年生から受験できます。
塾生は必須ですが、外部からの申し込みも可能で、娘の受けた回にも一般の受験生がいました。
試験形式は「適性検査Ⅰ(文系寄り)」と「適性検査Ⅱ(理系寄り)」の2科目で、それぞれ45分。
初めての受験だった娘は「学力テストより難しかった」と言っていました。
難易度と日々の学習の大切さ
問題は一見難しそうに見えますが、実際は 授業で習った基礎力をどれだけ理解しているか が試されている印象でした。
先生からも「結局は日々の授業を丁寧に受けることが大切」と言われています。
つまり、特別な対策よりも 毎日の学習習慣の徹底 が一番の近道。
模試を通して、基礎をしっかり積み上げることの重要性を実感しました。
勉強以外の情報力も試される
意外に大切だと感じたのは「一般常識や生活の知識」。
今回の模試でも、身近な題材(例:サービスエリアと道の駅の違い)をベースに、国語・算数・理科・社会の要素が絡んで出題されました。
適性検査では、一般常識とプラス、地域の情報や、伝統、文化、風習など、自分の暮らしている地域と関連した情報も、身に着けることが必須と言われています。
そのため、こども新聞は、テキストと同じくらいに重要な情報だと思いました。
こども新聞に限らず、地域の情報を得るには、地元新聞は有効です。
娘も「学校で習う勉強だけじゃ足りない」と実感したようです。
公立中高一貫校の受検対策としては、
- 子ども新聞を読む
- 地域や文化、身近な生活知識を家族で話題にする
- ニュースや時事問題に触れる
こうした取り組みが今後ますます必要だと感じました。
点数配分の重み
模試では1問あたりの配点が非常に大きく、5年生模試では6点~34点と幅広いです。
特に34点の作文問題では「200字以内でテーマに沿った文章を、原稿用紙ルールに従って書く」という形式でした。
1問で合否が左右されることもあるため、 1点の重みを意識する 必要があります。
「たかが1点、されど1点」この意識が受験本番に直結すると実感しました。
※配点が大きいのは、5年生の適性検査対策模試となります。
※6年生の模試や入試については、5年生時より問題数が多くなることもあり、1問に対する配点は6年生時の方が、少ないそうです。
自己採点で得られる学び
模試終了後すぐに自己採点をするのも大事な流れ。
娘のクラスでは、最後の34点問題が誰も書けず、全員マイナスに…。
「できなかった」と落ち込むのではなく、 仲間と振り返りをして学びに変える ことが大切だと思いました。
今後の課題とまとめ
今回の模試を通して見えた課題は、
- 日々の学習を丁寧に積み重ねること
- 一般常識や生活に根ざした知識を広げること
- 1点の重みを理解し、答案の完成度を高めること
初めての模試は緊張もありましたが、大きな収穫になりました。
これから受験本番までの1年間、この経験を活かして準備を進めたいと思います。
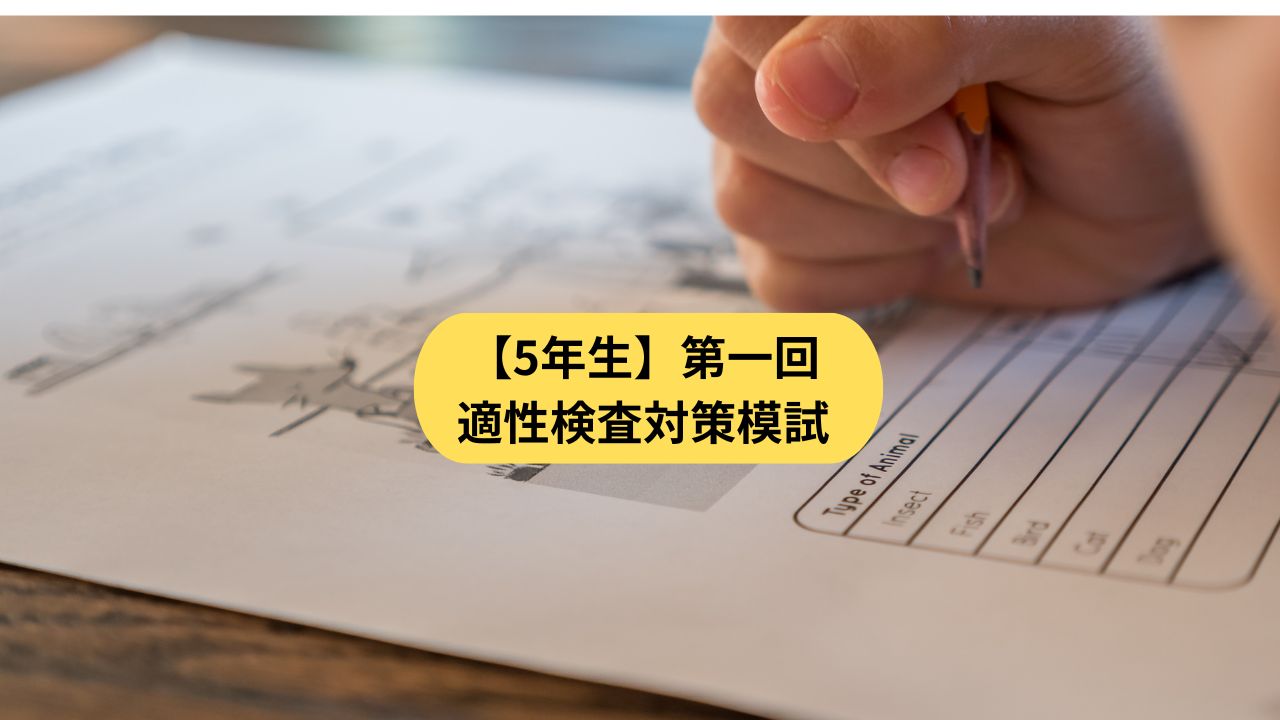


コメント