4月から娘は6年生になりました。
春休みの間も机に向かって頑張っていたので、最初の模試には期待していたのですが……。結果は本人にとってもショックな「惨敗」。
帰宅後の落ち込みように、私も胸が痛くなりました。
ただ、この模試で見えたのは「失敗」だけではなく、これからの学習で活かせる大きなヒントでした。
この記事では、娘と一緒に振り返った「失敗の原因」と「改善の方向性」、そして公立中高一貫校の適性検査で合格をつかむために大切なことを整理していきます。
点数取得の計画が裏目に
今回の大きな失敗は、解く順番の作戦ミスでした。
- 5年生の模試では、作文が34点と高配点 → 娘は「作文を最優先で解く」作戦を徹底。
- ところが、6年生から作文配点は13点になると耳にして、今回は「最初から順番に解く」作戦に変更。
結果、なんと実際の模試は まだ作文34点配点のまま。
しかも時間をかけすぎて最後の作文にたどり着けず、34点を丸ごと落とす痛恨の結果となりました。
📌 教訓
- 「最新の形式かどうか」を確認せず思い込みで作戦を変えるのは危険。
- 解ける問題・配点の高い問題を確実に取ることが、最も効率のよい戦い方。
もったいないミスをなくす
もうひとつの反省点は「漢字のケアレスミス」。
理系の問題で「並列」を「平列」と書いてしまい、不正解に。
適性検査は「漢字を間違えると不正解扱い」になるため、
- 書けない漢字はひらがなで書く
- 普段から「ていねいに書く」習慣を大切にする
こうした小さな意識が、数点の差を生みます。
問題を解くスピードを上げる対策
娘の口癖は「時間をかければ解けるのに」。
つまり、演習量不足と形式慣れ不足が原因です。
- 通常の塾の学力テストには慣れているが、適性検査特有の問題形式はまだ経験不足。
- そのため「考える時間」が長くなり、最後まで解けない。
📌 対策
- 適性検査形式の問題演習を増やす(フォローアップ冊子などを活用)。
- 解く順番・時間配分のシミュレーションを繰り返す。
「時間内にどう解き切るか」を日々の練習に取り入れる必要があります。
こちらの冊子(公立中高一貫校 適性検査対策模試 フォローアップ講座)は、適性検査対策模試を受けると付属して貰えます。
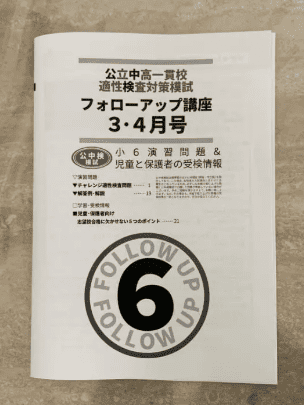
そして適性検査の例題や志望校合格に欠かせないポイントなど、受検に役立つ耳よりな情報が書かれていました。
適性検査の性質をふまえた合格戦略
模試の冊子にあった「志望校合格に欠かせない5つのポイント」を読んで、改めて大切だと感じたのは次の点です。
- 適性検査は教科書範囲がベース
- ただし、そこから発展した「生活や社会とのつながり」が重視される
- 基礎力+応用的に考える力+日常生活からの学びが合格の鍵
例えば、
- 理科で育てている植物 → 出題例に発展
- 家庭科の食育や社会科のリサイクル活動 → 記述問題につながる
つまり、学校生活や日常の中にヒントは無数にあるのです。
📌 ポイントまとめ
- 基礎(教科書範囲)は「入口」。
- その先に必要なのは「応用力」と「日常体験を知識に結びつける力」。
まとめ
失敗を未来への糧に
今回の模試は、娘にとって「惨敗」でした。
けれども、そこから得た気づきは合格への大切な一歩です。
- 配点と解く順番の見極め
- ケアレスミスを防ぐ習慣
- 適性検査形式への演習と慣れ
- 日常生活から学ぶ姿勢
これらを少しずつ積み重ねることで、模試の失敗は将来の成功につながる宝になります。
私自身も、結果だけに一喜一憂するのではなく、娘の努力や日々の学びを信じて支えていこうと思います。
「失敗は未来の糧」今回の経験をそう位置づけながら、次の模試に向けてまた一歩ずつ進んでいきたいです。
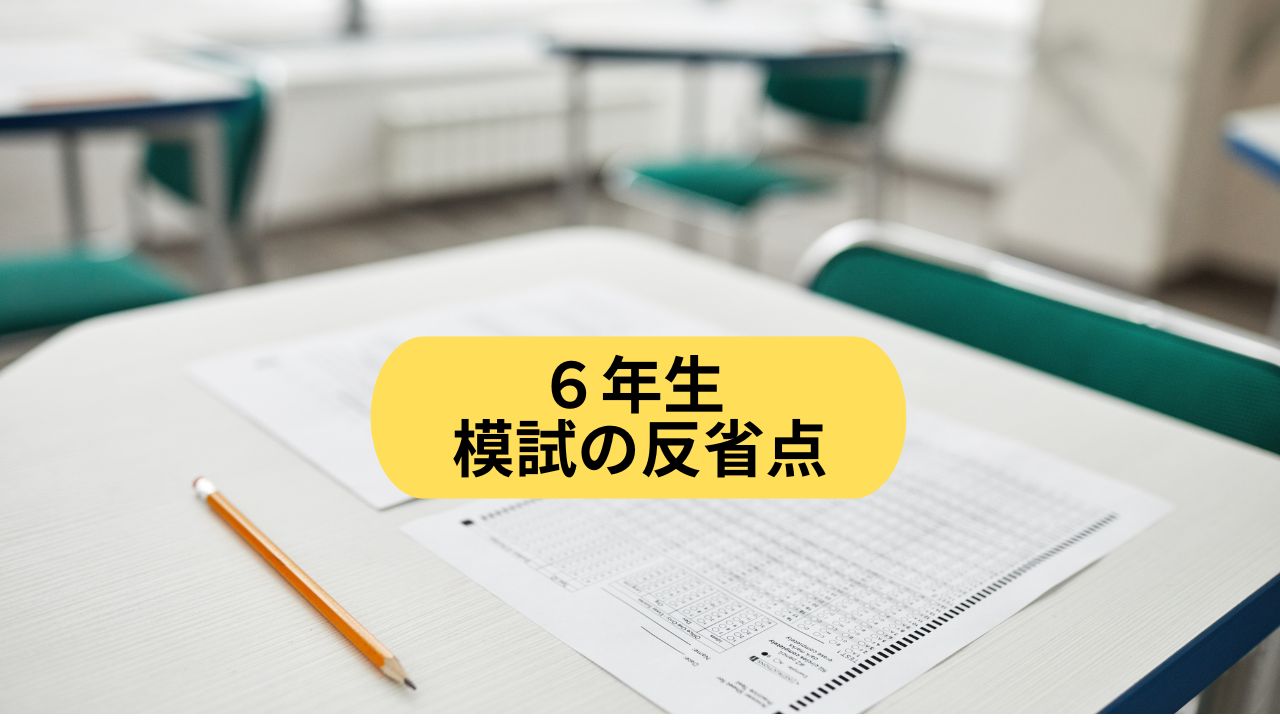


コメント