我が家の小学5年生の娘は、公立中高一貫校の中学受検を目指して塾に通っています。
この記事では、塾の授業で学んだ「分配法則を活用した計算スピードアップの方法」と「図形問題にどう役立つか」を整理します。そして、塾授業で得た知識を家庭学習にしっかりとつなげるための工夫や、宿題の取り組み方を具体例を交えてご紹介します。
中学受験に向けた勉強では、塾の授業をどう生かすかが合否を分ける大きなポイントになります。せっかく学んだことも、その場限りで終わってしまってはもったいないですよね。
日々の学びを積み重ね、効率的に受験対策へとつなげていきましょう。
少しユーモラスなエピソード(出席確認の俳句)も交えつつ、中学受験における算数の本質的な学び方についてまとめました。
オンライン授業と出席確認の工夫
娘の通う塾では、部活動や下校時刻の都合で通塾が難しい場合、オンライン授業を受けられる仕組みがあります。
その際、出席確認として先生からの「コメント課題」が出されます。
ある日の出席確認は「梅雨をテーマに五七五の俳句をつくろう」というものでした。
娘の作品は…

雨降ると
家で遊ぶの
つまらない
親としては苦笑いの一句。俳句の季語や表現の奥深さまでは理解できておらず、ただ言葉を並べただけのようにも見えました。
しかし、「自分の言葉で表現すること」自体が成長の一歩であり、学習の入り口だと受け止めています。
このような「脳の準備体操」は、中学受験の適性検査に通じる発想力・表現力を鍛える意図があるのだと感じました。
算数で学んだ「分配法則」と計算スピード
本題の算数の授業では、小数のかけ算を題材に「分配法則」を学びました。
分配法則とは
(a+b)×c=a×c+b×c(a + b) × c = a × c + b × c(a+b)×c=a×c+b×c
という基本法則で、中学以降の数学でも頻繁に登場します。
小学生の段階では単純な式変形に思えますが、計算の効率化に直結する重要な道具です。
分配法則で変わる計算例
例えば、
(25+3)×4(25 + 3) × 4(25+3)×4 を直接計算すると、28 × 4 = 112。
しかし分配法則を使えば、
25 × 4 + 3 × 4 = 100 + 12 = 112。
この単純な考え方が、二桁や小数点を含む計算、図形の面積・体積に応用できるのです。
図形問題での応用 面積・体積
中学受験算数では「図形の面積・体積」が最頻出分野のひとつ。
塾の先輩保護者に聞いても「もっとやっておけばよかった」と口をそろえる単元です。
ここで分配法則が大きな役割を果たします。
- 円の面積を分けて考える
例えば「半径の異なる円の重なり部分」などは、円の面積を分解して引いたり足したりする計算になる。
分配法則を知っていると、効率的に整理できる。 - 複雑な体積の計算
立体を分割して「簡単な立体の和」にする際にも、分配法則で計算量を減らせる。
つまり、分配法則は「計算スピードを上げる道具」であると同時に、図形問題をシンプルに整理する武器でもあるのです。
中学受験での実戦的な意味
受験本番で意外に差をつけるのが 「時間配分」 です。
知識量だけでなく、速く・正確に解く力が必要になります。
塾でも繰り返し強調されるのは次の3点です。
- 素早く → 分配法則で計算を簡単にする
- 正確に → 計算ミスを減らす
- 効率よく → 式を整理して時間を短縮する
娘にとっても「ただ暗記する算数」から「考え方を工夫する算数」への転換点になっていると感じます。
今後の課題
現時点での課題は、
- 分配法則を理解したうえで 自分で自然に使えるようになること
- 面積や体積など、受験頻出分野での応用練習を積むこと
です。
俳句のお話に戻れば、「言葉を工夫して自分の思いを表現する」ことと、算数の「式を工夫して効率的に解く」ことは、どこか共通しているのかもしれません。
まとめ
今回の塾の学びを通じて感じたのは次の2点です。
- 算数は工夫次第でスピードも正確さも変わる
分配法則を使いこなせば、面積・体積といった難問にも強くなれる。 - 日常の小さな学びも受験につながる
出席確認の俳句のように、一見算数とは関係ない活動も、発想力や表現力を育む訓練になっている。
中学受験は「勉強」だけでなく「考える力を伸ばす総合的な時間」でもある。
娘の学びを親の目線で支えながら、これからも受験に役立つ気づきをまとめていきたいと思います。
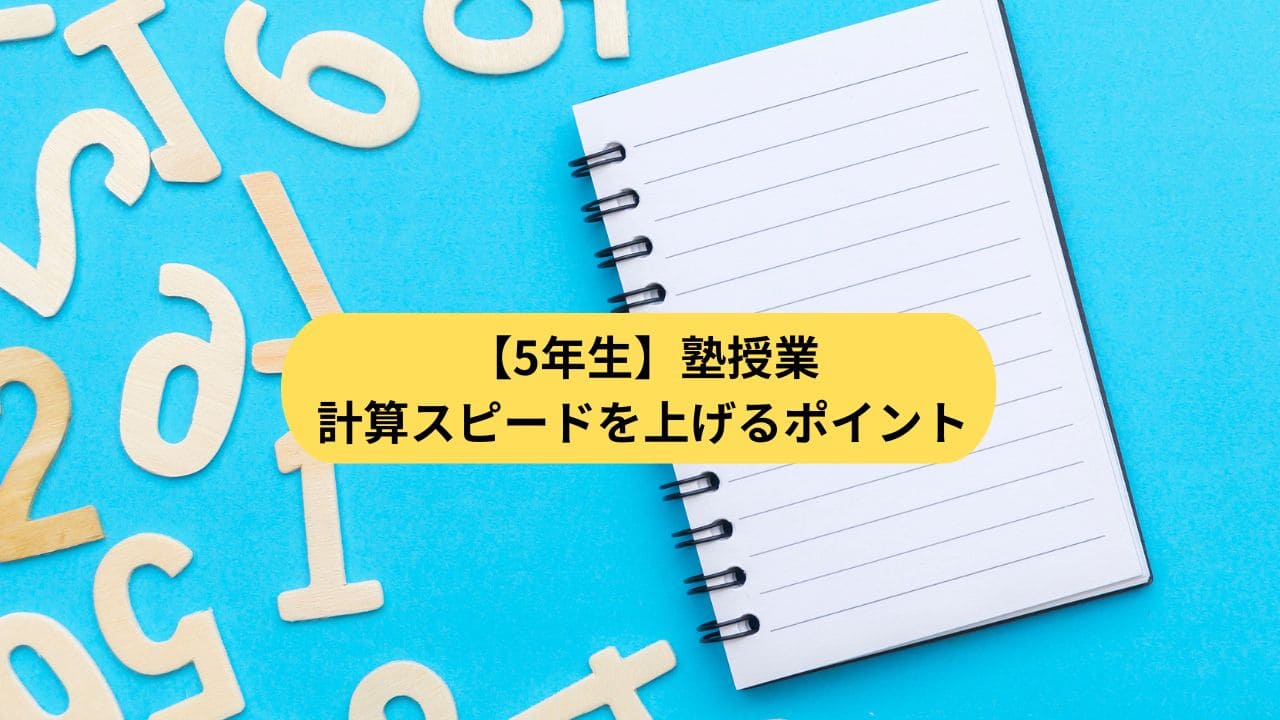


コメント