模試を通して気づいた「書き方の大切さ」
先日、娘が受けた模試を振り返ってみて、改めて「解答用紙の書き方ひとつで点数が左右される」ことを痛感しました。
私自身、親としては「内容が合っていれば評価されるはず」と思いがちでしたが、実際はそう単純ではありません。
字の見やすさ、消しゴムの使い方、解答の写し間違い…。
これらは学力そのものではなくても、試験結果を大きく左右する要素です。
この記事では、娘の体験談を交えながら、なぜ解答用紙をキレイに書くことが重要なのか、そして具体的にどう工夫すれば良いのかを整理してお伝えします。
解答用紙の書き方が重要な理由
模試や入試では、問題用紙と解答用紙が配られます。多くの場合、解答用紙に最終的な答えを書き込むことになりますが、この「書き方」の良し悪しは意外なほど結果に影響します。
- 見直しのしやすさが変わる
キレイに整えた解答用紙は、最後の数分で効率よく見直しができます。反対に、文字が乱雑で訂正だらけだと、どこを直したのか自分でも分からなくなり、致命的なミスを見逃しかねません。 - 採点者への印象
点数に直接関係はないとされますが、乱雑な解答より整った解答のほうが採点者にとって見やすく、無意識の印象に差が出ることは否めません。(※点数とは関係ありません)
親として見ていると、「もっと字を丁寧に…!」と言いたくなることもありますが、実際に娘が「キレイに清書した方が確認しやすい」と口にしたのを聞いて、子ども自身が気づいていく大切さを感じました。
消しゴムは極力使わない
模試の指導でよく言われるのが「消しゴムは極力使わない」ということです。
その理由は大きく3つあります。
- 紙が傷んで読みにくくなる
繰り返し消すと解答用紙がクシャクシャになり、最悪の場合は破れてしまいます。 - 消し跡が誤答に見えることがある
正しい答えを書いていても、消し跡が残ると「二重回答」と誤解される可能性も。 - 時間のロスにつながる
消すたびに時間を取られるので、制限時間内に最後まで解き切れなくなることがあります。
娘も最初はすぐに消しゴムを使うタイプでした。しかし、先生から「答えは一度問題用紙に下書きして、最後に清書すればいい」と教わり、だんだん意識が変わってきました。
清書のメリットと実践方法
解答を直接書かず、まずは問題用紙に下書きをしてから清書する。
この方法には大きなメリットがあります。
- 自己採点がしやすい
問題用紙に下書きが残っているので、模試後に答え合わせができます。 - 清書時にミスに気づける
実際、娘は清書の段階で「符号が逆だった!」と気づき、消しゴムを使わずに修正できました。 - 見直し時間を短縮できる
整った解答用紙は、最後の確認が一目でできるため、数点の取りこぼしを防ぐことにつながります。
ただし注意点もあります。
模試や入試によっては「問題用紙に書き込み禁止」という場合があるので、事前に確認が必要です。

実際に起きた「ありがちなミス」
ここからは、娘が実際に経験した「もったいないミス」を紹介します。
- 答えを書き忘れる
問題用紙には正解を書いていたのに、肝心の解答用紙が空欄。 - 写し間違い
記号問題で、問題用紙には「ア」と書いていたのに、解答用紙には「イ」と記入。 - 列をずらして記入(致命的!)
入塾当初、娘は解答欄を1段ずらして記入してしまい、大問ごと全て不正解扱いに。
試験終了直前に気づいて大慌てで直したそうですが、本番であれば命取りです。
親としては「正解を書いていたのに…」と思ってしまいますが、入試では採点されるのはあくまで解答用紙。
どれだけ実力があっても、記入ミスひとつでゼロ点になる現実は、子どもにもしっかり理解させる必要があります。
まとめ
キレイな解答用紙は合格への一歩
模試や入試本番は、ただでさえ緊張感に包まれます。
だからこそ、解答用紙をキレイに仕上げる習慣を早いうちから身につけておくことは、とても大切です。
今回のポイントを整理します。
- 解答用紙は極力消しゴムを使わない
- 答えはまず問題用紙に下書きしてから清書
- 清書した解答は見直しがしやすい
- 答えの書き忘れ・写し間違い・列のズレには要注意
親として今回の模試を振り返ると、ただの「失敗談」ではなく、本番に向けた練習のうちに気づけて良かった経験だと前向きに受け止めています。
子どもが実力を十分に発揮できるかどうかは、知識や学力だけでなく、こうした「ちょっとした工夫」にもかかっていると感じます。
これから受験を控えるご家庭の参考になれば幸いです。
お子さんが努力を無駄にせず、当日の力を最大限に発揮できるよう、心から応援しています。
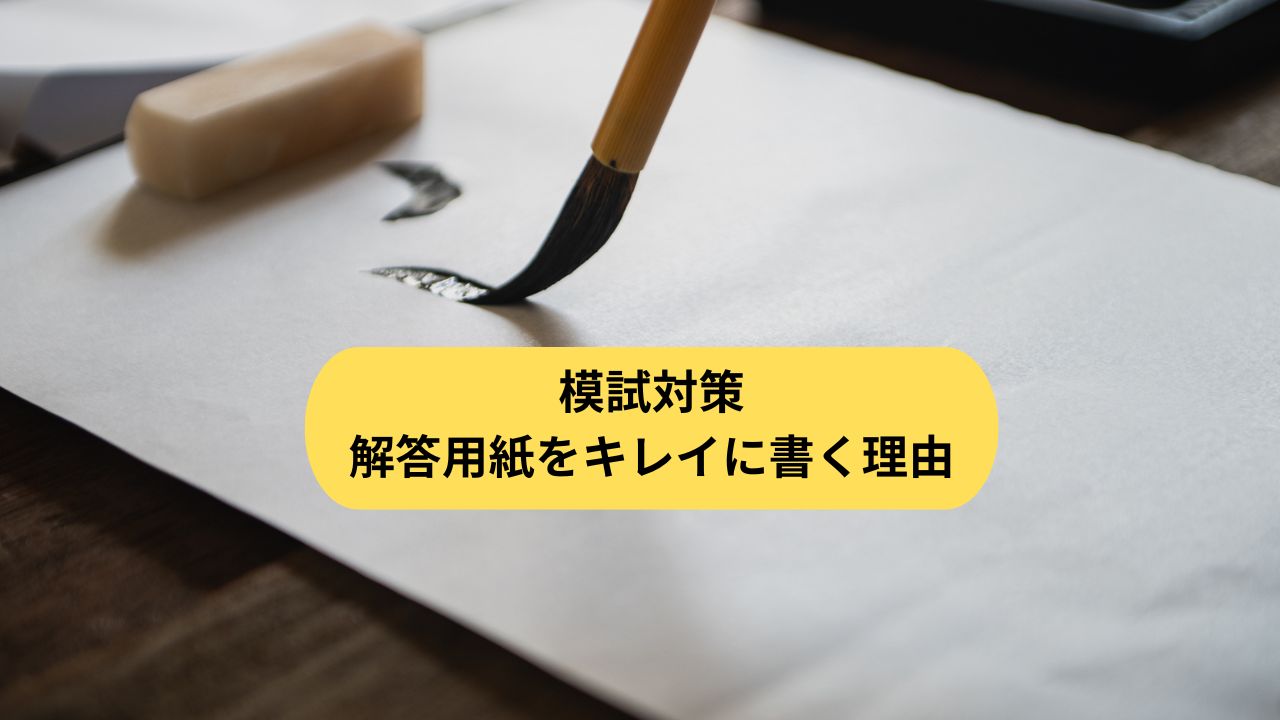


コメント