中学受験の季節が近づくと、家庭の空気も少しずつ張りつめてきます。
わが家でも、進学塾に通いはじめてから半年が経ち、娘の気持ちと私の思いとの間に小さな温度差を感じることが増えてきました。
この記事では、娘の塾での様子や、同じ学年を持つお母さん方との会話を通じて見えてきた「中学受験と親子の考え方の違い」をまとめます。体験談に加えて、公立中高一貫校受検にまつわる一般的な背景や、受験期を迎える親の心構えについても整理しました。
テストづくしの進学塾で見えてきたこと
小5の4月に塾へ通い始めてから、我が家はすっかり「テスト中心の生活」になりました。
- 毎月のテスト
- 適性検査対策模試
- 学力到達度テスト
と、気がつけば毎月何らかのテストが組み込まれています。11月は特にハードで、3週連続で試験が続きました。
このようにテストが続くのは負担も大きいですが、一方で 「場数を踏むことで、試験への耐性がつく」 という大きな効果もあります。塾の先生からも「結果だけでなく、テスト慣れを経験させることが大切」と言われ、改めて納得しました。
採点も学びに変える「左手の丸つけ」
塾で印象的だったのが、「左手で宿題の丸つけをする」というユニークな取り組みです。
国語の授業中、ある先生が「昔の学校には『右ポケットしか使ってはいけない』という、少し頑なな校則があった」という話をした流れで、「では今日は利き手ではない左手で丸つけをしてみよう」となったそうです。
一見遊びのようですが、これは脳を刺激し、新しい感覚を育てる効果もあるそうです。娘から話を聞いたとき、「受験勉強=詰め込み」というイメージが少し和らぎ、子どもの柔らかい発想や好奇心を生かす教育の大切さを感じました。
お母さん方が抱える「受験のモヤモヤ」
塾の送迎時は、いつも自然と「受験事情」の話になります。
- 公立中高一貫校を受けるべきか、地元中学から高校受験を目指すべきか
- 大学受験を見据えるなら、どちらが有利なのか
- 中学受験と高校受験、どちらが「賢い子」に育つのか
正解はなく、それぞれの家庭で悩みながら選んでいるのが現実です。
特に「中学受験に挑戦したい」と強く望む子どもと、「まだ高校受験でいいのでは」と考える親との間には、少なからず温度差があります。また、その逆で親が積極的で子どもが消極的な場合もあります。
我が家の場合、娘が「どうしても中学受験をしたい」と言い出したため、その思いを尊重しましたが、親の気持ちは常に揺れ動いています。
学力が一番伸びる瞬間とは?
「中学受験組と高校受験組、どちらが学力が高いのか?」
これは保護者の間でよく話題になりますが、私の考えは少し違います。
学力が最も伸びるのは「受験直前期」です。
- 中学受験なら小6の冬
- 高校受験なら中3の冬
つまり、「どちらが学力が高いのか」ではなく、「どの時期に一番頑張るか」の違いでしかありません。
子どもによって「火がつく時期」は異なるため、そのタイミングを見極めるのが親の大切な役割だと思います。
公立中高一貫校と「母の覚悟」
公立中高一貫校では、中学から入学した生徒と高校から入学した生徒が同じクラスになることは少ないです。しかし、高校入学組が急激に学力を伸ばしてくることもあり、「せっかく中学受験をしたのに追い抜かれてしまうのでは?」と心配する保護者の声も耳にします。
一方で、こんな考え方をするお母さんもいます。

公立中高一貫校の受検は、くじ引きみたいなものだから合格出来ればラッキーよ~。大当たり、大当たり!
肩の力を抜いて挑む姿勢は、結果的に子どもの力を引き出すのかもしれません。
実際に、そうしたご家庭のお子さんが合格しているのを見て、私自身も「親の構え方次第で、子どもの受験生活の色合いも変わる」と感じています。
まとめ
親子で温度差をすり合わせながら進む
中学受験は、親の思いと子どもの気持ちが必ずしも一致するわけではありません。
だからこそ大切なのは、
- 子どものやる気を尊重する
- 親は過度に焦らず環境を整える
- 受験期を「親子の経験」として共有する
ことだと思います。
来年の今ごろ、わが家も結果が出ているはずです。
そのときに「悔いはない」と言えるように、これからも娘と二人三脚で歩んでいきたいと思います。
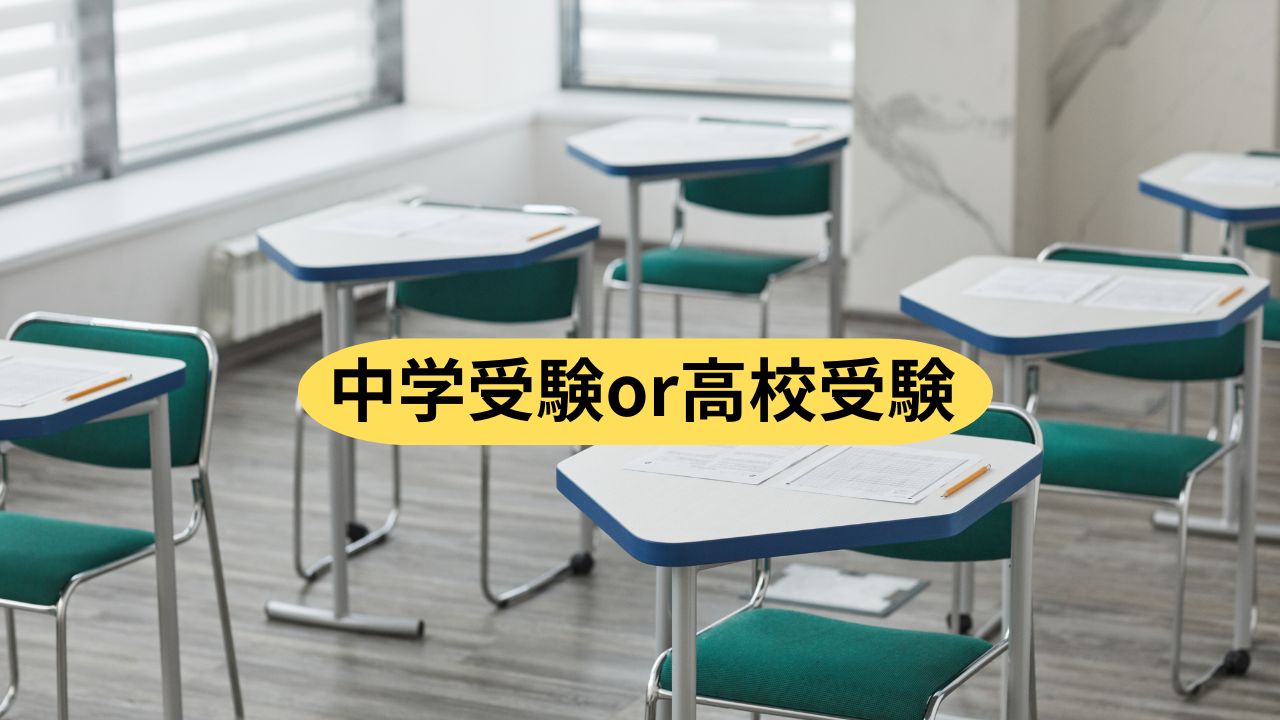


コメント