わが家の娘は現在、小学5年生。
中学受検を目指して塾に通い始めて数か月が経ちました。
先日、2回目となる「適性検査対策模試」の結果が返却されました。点数だけを見れば反省点も多く、「まだまだこれから」という内容でしたが、模試を通じて得られた学びは非常に大きかったと感じています。
この記事では、娘が体験した模試の内容や反省点をもとに、公立中高一貫校の適性検査に共通する出題形式の特徴・得点力を上げるための工夫・親として気づいた指導のポイントをまとめました。
同じように「模試で思うように結果が出なかった」「どう点数に結びつければよいか悩んでいる」というご家庭に、少しでも参考になれば幸いです。
適性検査と一般的な学力テストの違い
まず押さえておきたいのは、「適性検査」と「通常の学力テスト」の違いです。
- 通常の学力テスト
計算・知識・読解など、明確に答えが決まっている問題が多い。
基礎学力を徹底し、演習を重ねることが基本対策。 - 適性検査
知識だけでなく「思考力・表現力・応用力」を問う。
選択肢ではなく、自分の言葉で答えを書く問題が中心。
日常生活の体験や社会の出来事を題材にすることも多い。
娘の塾でも先生から「難しく感じても素直に読んで素直に考えることが大切」と指導がありました。つまり、知識を丸暗記する勉強だけでは不十分ということです。
適性検査Ⅰ(文系)漢字・文章読解・作文
漢字は基礎力+表現の土台
実は、公立中高一貫校の試験では「漢字の読み書き」そのものが出題されない場合があります。
しかし、多くの合格者が口をそろえて言うのは、
「もっと漢字を練習しておけばよかった」という反省。
理由はシンプルで、解答に使う言葉で漢字を誤ると減点されてしまうからです。
娘も「書き慣れていない字は時間がかかるし、正確さに不安が残る」と感じていました。
👉 親の工夫ポイント
- 漢字練習は「テストのため」というより「表現の道具」として意識させる
- 模試や宿題で書いた解答に、漢字ミスがないか親子で一緒に確認する
文章問題の穴埋め・記述
今回の模試でも、空欄に3文字や5文字を入れる記述問題が多く出題されました。
似た言葉を書いても、意図が伝わらなければ減点される厳しさがあります。
娘が工夫していたのは
- 消去法を用い、まず不適切な選択肢を消していく
- 「なぜ?」と問われたら必ず最後に「〜から。」で締める
こうした「答え方のテンプレート」は地味ですが、減点防止に役立ちます。
作文問題(150〜200字・配点大)
作文は配点が大きく、5年生の模試では 34点満点中32点 を取ることができました。
前回は時間切れで白紙提出=0点。今回は最初に作文から着手したのが功を奏しました。
ただし、細かい減点もありました。
例)
「甘い物を食べたりして休けいしています。」
→ 「食べたりして」は冗長で不適切。「食べて」と簡潔に表現すべき、と指摘されました。
作文で重要なのは
- 字数・段落構成・句読点などの指示を守る
- 独創性を加えつつ、論理的な流れを意識する
- 日常生活から自分の経験を交えて書く
作文は一朝一夕では伸びません。模試や日記を通して日頃から表現力を養うことが必要だと痛感しました。
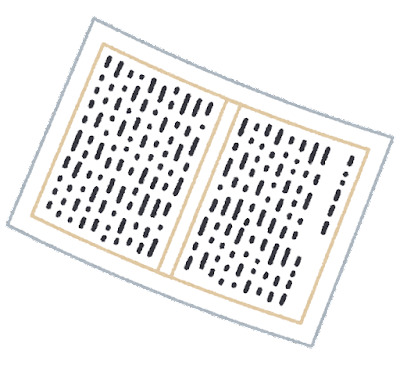
適性検査Ⅱ(理系) 文章読解型の理科・算数
一見「理系」と書かれていますが、実際には文章を読んで答える文系寄りの問題が多いのが特徴です。
今回の模試では、
- 種子の発芽条件を調べる「対照実験」
- ゲーム(オセロ)の勝敗を推理する問題
が出題されました。
理科の実験問題では、娘は「対照実験=変える条件は1つだけ」と学校で習った知識をそのまま書き、不正解。
正解は「空気だけでなく温度も違っている」と具体的に条件を指摘する必要がありました。
👉 ここからの学び
「教科書的な定義をそのまま覚える」だけでは対応できない。
実際の状況を正しく読解し、「なぜそうなるのか」を答えられる柔軟さが求められます。
模試を通して得た親子の学び
今回の模試で感じたことは、「知識を知っている」ことと「試験で使える」ことは別物だということです。
娘自身も、学校で習ったことをそのまま書いて不正解だったという経験を通じて、問題文を丁寧に読み、条件を整理して答える力の大切さを学びました。
親としては、
- 点数の善し悪しよりも「なぜ間違えたのか」を一緒に分析する
- 成績表は反省と改善の材料として前向きに活かす
こうした姿勢を大切にしたいと思います。
まとめ
模試は「失敗する場」として活用する
模試は結果に一喜一憂する場ではなく、本番前に失敗できる貴重な場です。
- 漢字や表現は普段から丁寧に
- 作文は早めに着手・指示通りに構成
- 理系問題も読解力がカギ
こうしたポイントを意識して、次の模試や入試本番に活かしていきたいと思います。
同じように受検を目指すご家庭にとっても、「こういう工夫があるのか」と感じてもらえたら嬉しいです。
親子で模索しながら、一歩ずつ前進していきましょう。



コメント