中学受験を目指す家庭にとって、塾との連携は欠かせません。
一方で、小学校高学年は心身ともに大きな変化が訪れる時期。部活動や反抗期など、勉強以外の要素も受験生活に影響を与えます。
この記事では、わが家の「塾の個別懇談会」の体験をもとに、
- 志望校と学力の現状確認
- 通塾とオンライン授業の違い
- 思春期と反抗期の受験への影響
- 塾講師が語った「反抗期の定義」
について整理し、中学受験を目指すご家庭に役立つ視点をまとめました。
個別懇談会で確認された志望校
先日の塾懇談会では、最初に「志望校はどこですか?」と質問されました。
わが家は、公立中高一貫校を志望しています。先生からは、
- 現状の学力で6年生なら「時間が足りない」
- しかしまだ5年生なので「残り1年5ヶ月の努力次第で十分可能性はある」
と具体的な見通しをいただきました。
つまり、現時点の成績よりも、残された時間をどう使うかが重要ということです。
通塾かオンラインか 塾側の懸念点
次に話題になったのは「授業形態」でした。
わが家では部活動や委員会の影響で帰宅が遅く、通塾に間に合わない日が増えています。そのため、オンライン授業に頼ることが多くなっていました。
先生からは次のような指摘がありました。
- オンライン授業は便利だが、子どもの様子が分かりにくい
- 本人が理解しているかどうか、対面より判断が難しい
- 突発的な利用なら有効だが、標準授業がオンライン化すると「塾本来のサポート」が十分にできない
- 緊張感がもてない
この指摘から学べるのは、オンライン授業は補助的な選択肢であり、基本は通塾が望ましいという点です。
塾は単に知識を教える場ではなく、「生徒の学習態度や理解度を観察し、適切にサポートする場」でもあるからです。
親のサポート体制が受験のカギ
塾講師からは「親のサポート体制」についても言及がありました。
- 送迎や生活リズムの管理
- 家庭学習の声かけ
- 子どもの精神的な支え
これらを整えることで、塾と家庭がチームとなり、受験に向かいやすくなるとのことでした。
中学受験は「子どもだけの戦い」ではなく、親・塾・本人の三位一体で取り組むもの。
改めてサポート体制を整える必要性を実感しました。
受験と反抗期 親の悩み
もう一つの大きな課題は「反抗期」です。

わが家の娘も例外ではなく、イライラが増え、気に入らないと口をきかなくなることもあります。
中学受験に取り組むうえで、この状態をどう理解し、サポートすればよいのか。
懇談会で思い切って先生に相談してみました。
塾講師が語った「反抗期の定義」
先生の答えは非常にシンプルでした。
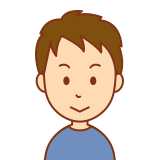
自分で段取りを立て、責任を持ってやり切れるなら、それは反抗期。
そうでなければ、ただの甘えです。
この言葉は目から鱗でした。
私自身も「反抗期」という言葉に逃げてしまい、子どもの甘えを正面から見つめることを避けていたのかもしれません。
反抗期かどうかを見極めるよりも大切なのは、子どもが自立した行動をとれているかどうか。
この視点を持つことで、親の対応も変わってきます。
まとめ
受験は「1人ではない」
今回の懇談会を通じて強く感じたのは、次の3点です。
- 志望校合格は「現状」ではなく「残り時間の使い方」で決まる
- オンライン授業は便利だが、塾との連携を考えると「通塾」が基本
- 反抗期も受験の一部。自立か甘えかを見極め、親が冷静にサポートする
中学受験は、子どもひとりだけで挑むものではありません。
親、塾、そして子ども自身の三者がチームとなって進む道です。
わが家と同じように悩みながら受験に挑むご家庭へ
「受験は1人ではない」という言葉を心に留め、周囲の力を借りながら前進していただければと思います。
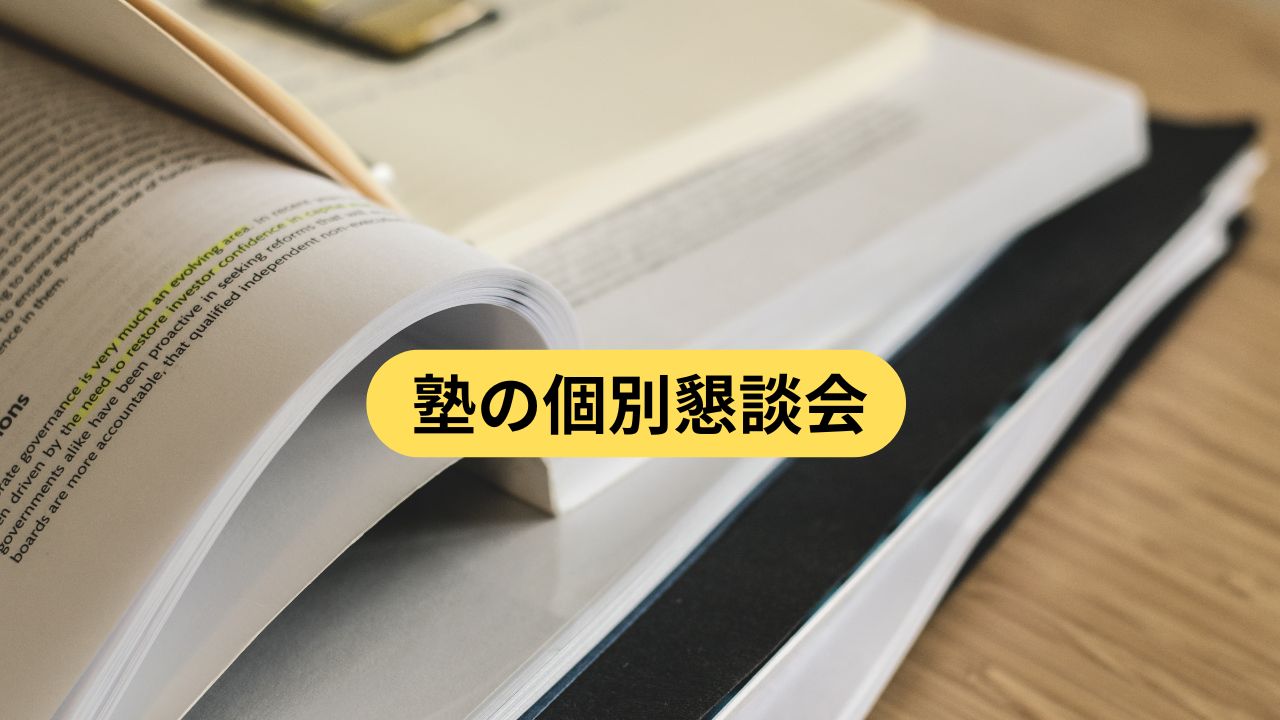


コメント