わが家の娘は現在小学5年生。公立中高一貫校の中学受検を目指して日々奮闘しています。
公立中高一貫校の入試は「適性検査」という形式で、単なる知識の丸暗記ではなく、生活に結びつけた思考力や表現力が試されるのが特徴です。ですが、その基盤となる知識、とくに社会科の暗記は避けて通れません。
今回は、塾で娘が体験した「社会の語呂合わせ授業」について、そして同時期に始まった反抗期との向き合い方について、親の目線からまとめたいと思います。
地理の基本を楽しく覚える
今週の社会の授業では、日本の位置や国土、周辺の国々について学んだそうです。
特に印象に残ったのが「日本の最端の島を覚える授業」。授業後の娘は楽しそうに私にこう話してくれました。
先生は、お昼休み明けの眠気が残る時間に「えーと、みんな起きてるよな?」と声をかけました。そこから「起きてるよな」をキーワードにして、日本の最端の島を語呂合わせで紹介してくれたのです。
- 択捉島(えとろふとう)=最北端
- 南鳥島(みなみとりしま)=最東端
- 沖ノ鳥島(おきのとりしま)=最南端
- 与那国島(よなぐにじま)=最西端
「えーと(択捉)・みな(南鳥)・おきてる(沖ノ鳥)・よな(与那国)」
まるで眠気覚ましの合図のようなフレーズ。娘もすぐに覚えてしまいました。
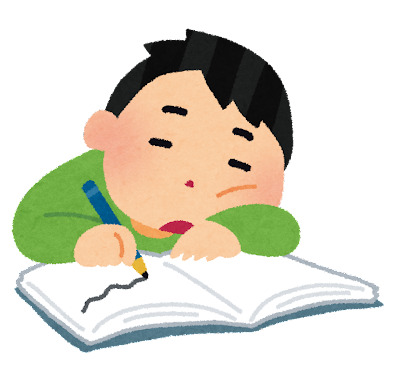
先生のオリジナルではなく、生徒にわかりやすく楽しく学んでほしいと工夫して調べたものだそうです。子どもたちの集中力が途切れる時間帯に、笑いを交えながら記憶に残る工夫をしてくださる姿に、親としてもありがたい気持ちになりました。
社会科は「生活に根ざした学び」
また、日本の国土と周辺の国々についても触れました。
- 北方領土、尖閣諸島、竹島 → 国際問題につながる地理
- 日本の 森林率(約3分の2が森林) → 人口が都市部に集中する理由
- 東北地方の田んぼの多さ → 気候・地形と生活の関わり
- 沖縄の住宅の工夫 → 台風対策として平屋や防風林を利用
社会は暗記科目と思われがちですが、このように「生活にどう関わるか」を結びつけると理解が深まり、適性検査にも直結します。
娘も「社会って覚えるだけじゃなくて、暮らしと関係しているんだね」と気づきを口にしていました。
受験と反抗期が同時に訪れる現実
しかし、親の立場としては楽しい授業ばかりを見守っていられるわけではありません。
中学受験を意識し始めた小学5年生という時期、わが家には 反抗期 という壁も同時に訪れました。
娘は、都合の悪いことには沈黙を貫き、機嫌を損ねると数日口をきいてくれないこともあります。親としてどう接すればいいのか、正直戸惑う場面も増えました。
ただ、この「反抗期」も成長の一部。親としてはイライラをぶつけるのではなく、「聞く耳を持つ余裕」をこちらが持つこと が何より大切だと感じています。

親子で見つけた学びのヒント
今回の塾の社会授業から学んだことは2つあります。
- 楽しく覚える工夫が、記憶の定着を助ける
語呂合わせや身近な生活との関連付けは、受験だけでなく一生の学びに役立つ。 - 反抗期は親にとっても学びの時間
中学受験と反抗期が重なるのは大変ですが、「子育ては修行」という言葉の通り、親も成長を求められているのだと思います。
中学受験は単なる知識の勝負ではなく、家庭全体の成長の時間でもあると、改めて実感しました。
まとめ
塾の授業で娘が学んできた「社会の語呂合わせ暗記法」。一見すると単なる覚え方の工夫ですが、そこには「生活に根ざした学び」や「親子で共有できる発見」が隠れていました。
さらに、反抗期と受験期が重なるという現実は決して楽ではありませんが、その中でも小さな気づきを積み重ねることが、親子にとっての大切な経験になると感じています。
中学受験は「勉強」だけではなく「親子の成長の物語」でもある。そんな思いを込めて、これからも日々を綴っていきたいと思います。
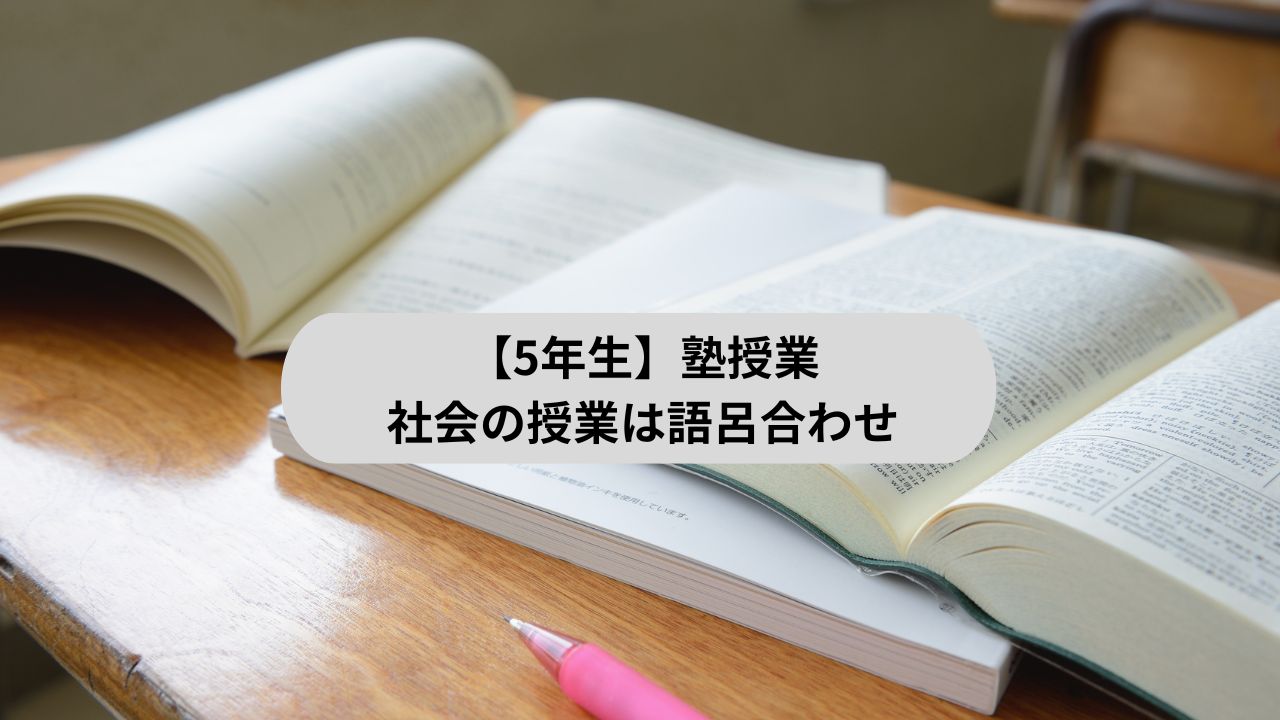


コメント