中学受験を目指す家庭にとって、算数は合否を大きく分ける最重要科目です。その中でも特に多くの受験生を悩ませるのが「図形問題」。
今回は、実際に塾で行われた 図形の先取り授業 をもとに、受験に直結する学び方のポイントや、家庭での活かし方を整理します。
図形が中学受験で難関とされる理由
算数のなかでも図形分野は、次の理由から「差がつく単元」とされています。
- 計算量が多い → ミスが連鎖しやすい
- イメージ力が必要 → 図を正確に描けないと混乱する
- 解き方が複数ある → 柔軟な思考力が問われる
実際、先輩受験生たちも「最後まで図形が一番苦手だった」と口を揃えます。
だからこそ、 早めの先取り学習 が大きな武器になるのです。
【よくある失敗例】計算ミスが雪だるま式に広がる
例えば、あるテストで娘は最初の計算を一つ間違えただけで、連続する3問すべてを落としました。
「最初の答えが次の問題の条件になる」形式では、 1つの誤答がその後すべてに影響 してしまいます。
👉 この経験から学んだことは、
- スピード重視よりも 正確性の確保 が先
- そのために 計算式を整理する工夫(分配法則の活用など) が必須
ということでした。
先取り授業で学んだ「分配法則」の活用
塾の先生によれば、図形分野では小学生のうちから「分配法則」を意識すると計算が格段に楽になるそうです。
例えば図形の面積計算では、
- 面積を分けて計算する
- 式を整理してシンプルにする
といった工夫で 計算ステップを減らし、ミスを防ぐ ことができます。
中学生で本格的に習う内容を、小学生の段階で「先取り」することで、受験本番で余裕を持てるのです。
図形を解きやすくする基本
ノートに正確に書き写す
授業では「図を必ず自分で書き写す」ことを徹底していました。
こちらは、娘が図形を書き写したノートになります。
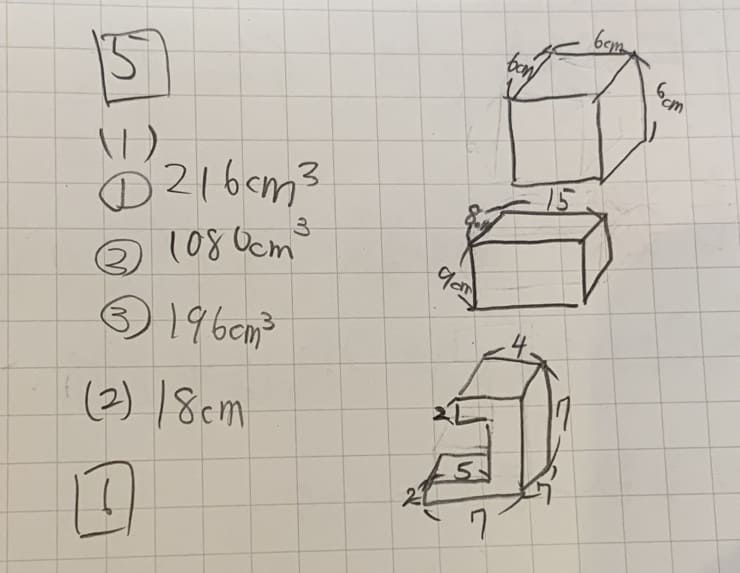
実際に娘のノートを見ても、板書をそのまま真似るだけでなく、線を引き直したり角度に印をつけたりすることで、 考えるためのヒントが自然と浮かんでくる ようになります。
この「手を動かして図を描く」習慣は、家庭学習でもぜひ取り入れたいポイントです。
多角形の内角の和を一瞬で求める方法
授業では、多角形の内角の和の公式を学びました。
(角の数−2)×180°(角の数 − 2)×180°(角の数−2)×180°
例えば、
- 五角形 → (5−2)×180=540°
- 六角形 → (6−2)×180=720°
多角の角については、娘のノートにも、五角形と六角形に対角線が引いてあります。
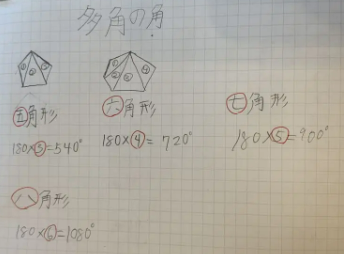
このように、実際に多角形に対角線を引くことで「なぜこの式で求められるのか」を体感できます。
図形問題に強い子は、このように 公式の意味を理解しながら覚えている のです。
三角形の外角と「くさび型」の角
さらに授業では、5年生向けに「外角」や「くさび型」の角の求め方も扱いました。
- 三角形の外角は「2つの内角の和」で表せる
- くさび型は「∠A+∠B+∠C=∠D」で求められる
どちらも 同位角・錯角の性質を応用 すれば導けるため、論理的に説明できるようにすることが重要です。
下画像は、娘のノートの「三角形の外角」と「くさび型」です。
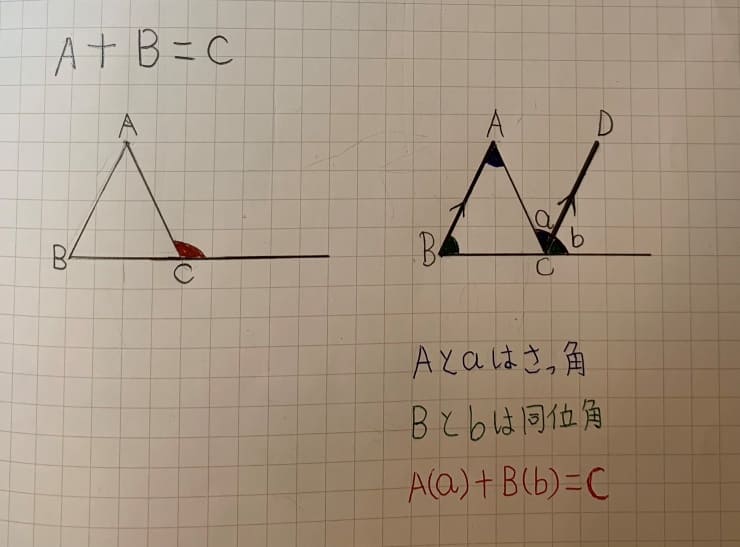
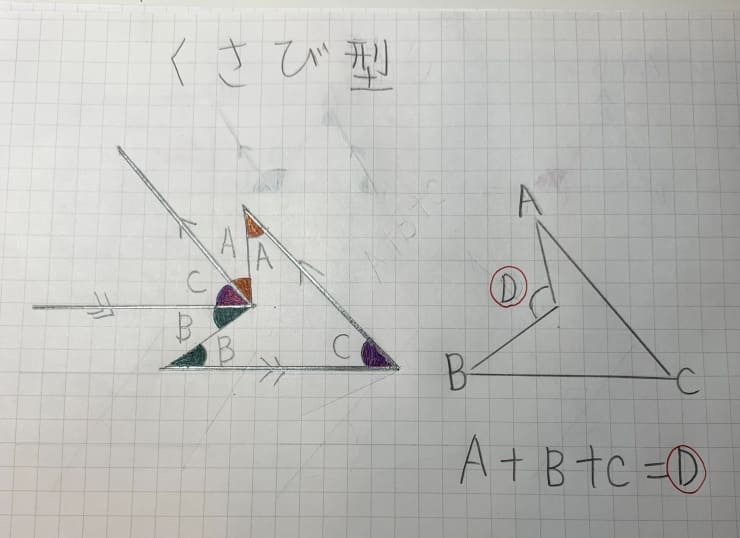
👉 ポイントは「答えだけ覚えるのではなく、導き方のプロセスを理解する」こと。
夏休みこそ「図形の苦手克服」のチャンス
塾の先生からも「受験は夏休み中が勝負」と言われています。
特に図形は反復練習なしでは定着しにくいため、夏休みは じっくり図形に取り組む絶好の時期 です。
- 過去に間違えた問題をやり直す
- 自分の弱点パターンを洗い出す
- 図を丁寧に描き直す習慣をつける
これらを徹底することで、秋以降の模試や本番に大きな自信を持てるようになります。
まとめ
図形は「早めの先取り+正確な理解」で得点源に
中学受験における算数・図形は、
- 計算ミスのリスクが大きい
- 柔軟な思考力が必要
という難しさがあります。
しかし、今回の授業で学んだように、
- 分配法則など先取り学習で「ミスを減らす工夫」を身につける
- 図を自分で描き、公式の意味を理解する
といった取り組みを積み重ねることで、図形はむしろ 差をつけられる得点源 になります。
夏休みは図形克服の大チャンス。親としても「計算ミスの連鎖を防ぐ工夫」や「学習習慣の支え」を意識して、家庭でのサポートを続けていきたいと思います。
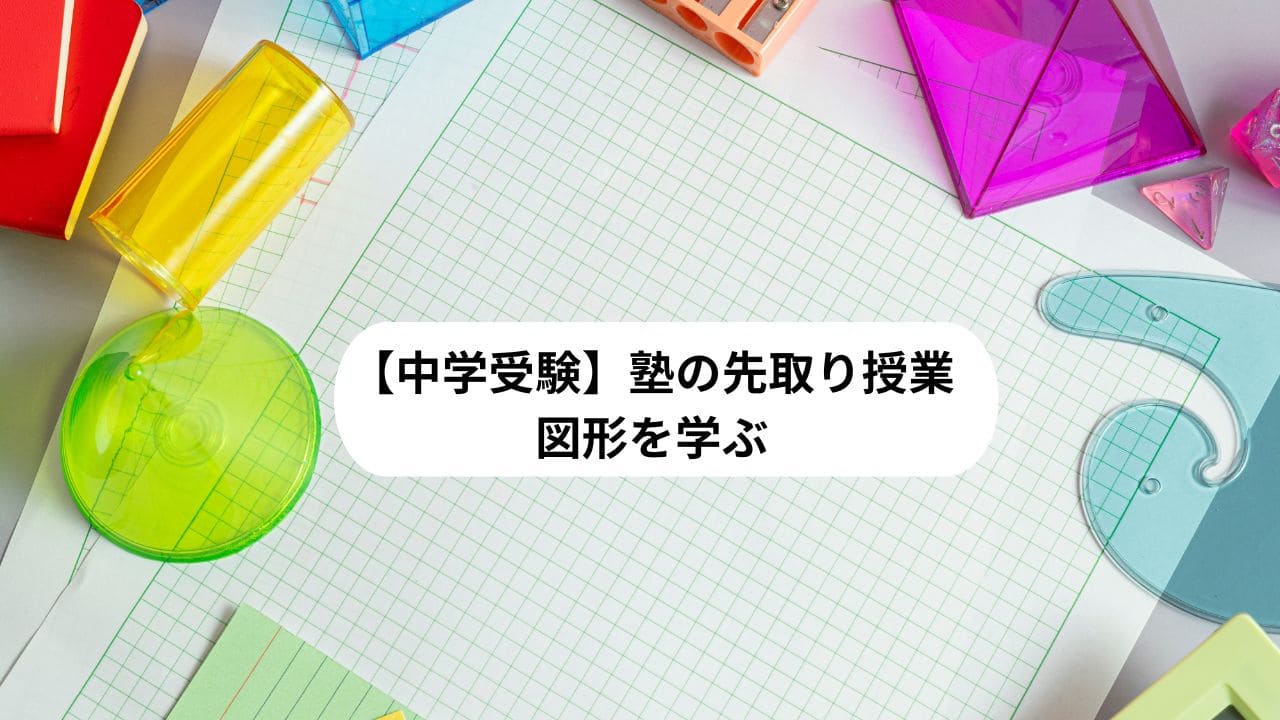


コメント